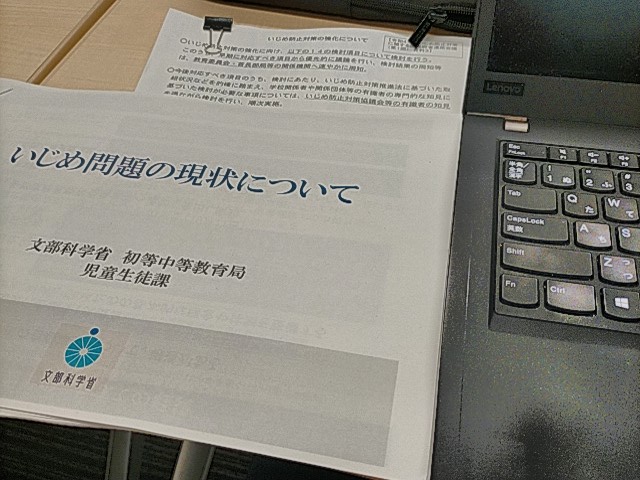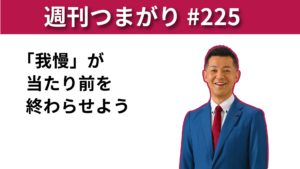都内に足を運び、文科省初等中等教育局児童生徒課より、いじめ問題の現状についてレクチャーをしていただきました。

資料:https://www.mext.go.jp/content/20211122-mext_jidou01-000019036_03.pdf
大津市をはじめとした深刻ないじめの事件を背景に、2013年9月にいじめ防止対策法が制定されました。現在、いじめの認定件数は船橋市も含めて右肩上がりの状況です。ですが、これは「いじめを早期に細やかに捕捉している」として、文科省でも肯定的に評価しています。
いじめが重大化していく背景に、担任の先生が抱え込んでしまう、表に出さないようにするということがあり、問題を初期のうちに早めにオープンにして学校全体として取り組むことが重要です。
全国的に見ると都道府県によって児童数あたりの認定件数に差がありますが、それ以上に公立と私立の差もが顕著とのことでした。
かつては、客観的に見ていじめられているかどうか、いじめられた側にも責任があるといったような取扱いがされていましたが、いじめ防止対策法により、より被害者目線を重視し幅広くいじめを認定することになりました。具体的には「子どもが心身の苦痛を感じている」か否かといった、被害者の主観を重視していします。ただ、残念ながら現場の先生方には未だ法の趣旨が浸透しきれていないところもあり、より周知・啓発のための研修が必要です。
人間が集団生活をしていく中で、大人であってもいじめの問題はあり、子どもの世界でも絶無とすることは困難でしょうが、問題が深刻になる前に対応することはできあるはずです。
船橋市では2013年のいじめの認知件数は2,911件でしたが、直近の2022年は8,181件と2倍以上になっています。また、いじめ重大事態といわれる、①生命、心身又は財産に重大な被害、②長期の欠席(年間30日を目安)を余儀なくされている深刻なケースに関する積極的な掘り起こしや対応を進めてきています。
今後は、学校や子ども達のこと全般的な問題に対応する常設の総合相談窓口の設置が求められます。国としても先進自治体の取り組みなどの調査を進めているようですが、できる自治体から始めていくことも大切です。またいじめの対応が不適切であった場合の懲戒処分の規定は各自治体によってまちまちであり、より厳格化するべきであるとの意見も出ています。

文科省からお話を伺うだけでなく、超党派でつくったいじめ防止法をリードした小西ひろゆき参議院議員、立憲民主党千葉県議会代表の入江晶子県議、田畑直子千葉市議、千葉県弁護士会の村山先生と意見交換を行いました。他自治体の現状や国・県・法曹界から見た視点など多角的な視点で現状の課題を深掘りすることができました。
他の「学校」記事一覧
-
 週刊つまがり
週刊つまがり
【週刊つまがり動画配信 #225】「我慢」が当たり前を終わらせよう
先日、仕事の関係で、「介護現場における暴力・ハラスメント」をテーマにした研修を受けてきました。県内各地から、施設やデイサービスで働く生活相談員の方々、約100名が集まり、主にカスタマーハラスメントについて学ぶ内容でした。 […] -
 週刊つまがり
週刊つまがり
【週刊つまがり動画配信 #209 】夏休み明けと不登校
夏休みが終わり今週から学校が始まっていますね。やっと子ども達のお昼の準備から解放されたと感じる親御さんも多いと思いますが、一方で夏休み明けは、不登校が増えやすい時期でもあります。 長い休みで生活リズムが乱れたり、宿題など […] -
 週刊つまがり
週刊つまがり
【週刊つまがり動画配信 #206 】市立船橋高校野球部がんばれ!
全国的にも部活動が盛んな市立船橋高校ですが、この夏、3年ぶり7回目の甲子園出場が決まりました! 1988年に市立船橋高校野球部が甲子園に初出場した際には、まちなかから人がいなくなり、皆でテレビの前で応援した記憶があります […] -
 活動報告・お知らせ
活動報告・お知らせ
船橋一直線!129号 親愛なる船橋の皆様へ
船橋一直線のつまがり俊明 皆さん、こんにちは。つまがり俊明です。船橋生まれ、船橋育ち、47才です。20歳の時に政治を志し、いつかはふるさと船橋の市長になりたいと思い研鑽を積んできました。民間ベンチャー企業を皮切りに、総務 […]