昨日9月25日に「つまがりに期待するもの」ミーティングを行いました。
この概要について報告します。
リアル、オンライン含めて25名ほどご参加いただき、次のことを目的に実施しました。
- なぜつまがり俊明を応援するのか言葉で語ってもらうことで、市民から出てくる生の言葉を今後の活動に生かしていきたい。(政策・広報物・演説・キャッチコピーなど)
- 参加者同士がつながる交流の場としたい。

参加者から次のようなコメントをいただきました。
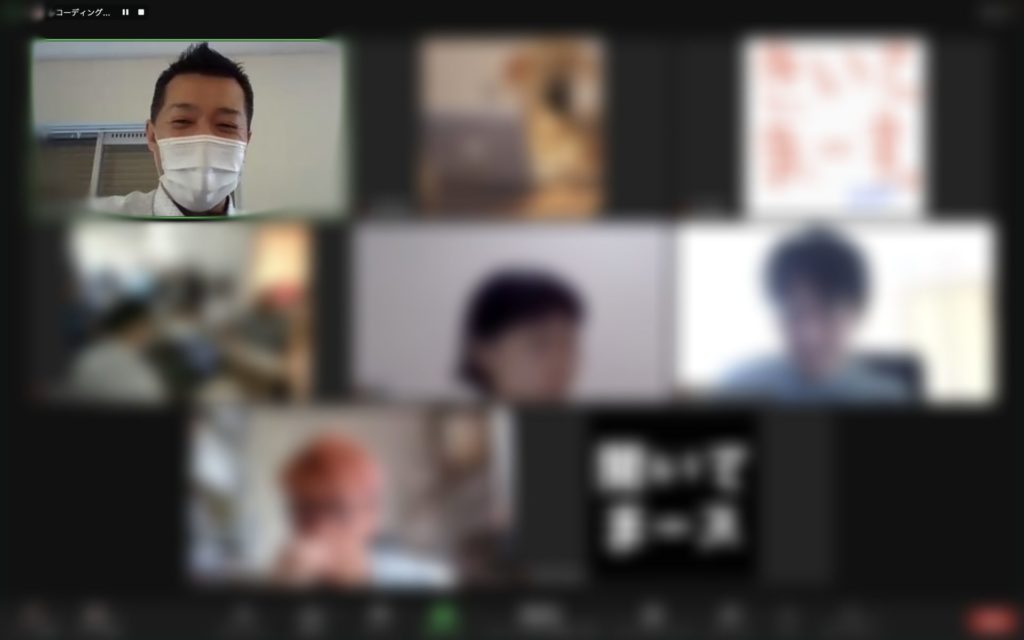
- 当園で行っている幼児教育に理解をしてもらっている。
- 公平な姿勢に安心感
- 多角的な角度で子供教育の姿勢が共感できる
- インクルーシブ教育を共に進めていきたい

- 困っている人たちに寄り沿っていくことは行政の大切な仕事であり、そこに注力していることが市民の安心につながる。
- 普段から市民の声をキャッチアップしてその人らしい暮らしができるようにしていくことが大事。
- 道路や産業などソフト・ハードの両面での住みやすいまちづくりを。
- 忖度しない情報の発信を今後も議員として継続してほしい。
- 都心に勤めていて地域のつながりが薄いのでこういった交流会を開いてもらえるのは良い。
- 日頃から市民のニーズをくみ取る姿勢は良い。
- 教育上障害のある子、ない子を別々に教育する現場環境に対して疑問を感じる
- 子どもに障害があり誰に相談してよいかわからず、国会議員の勉強会などに参加していた。地域の議員と繋がった方がより力になってくれるとの助言を元に知り合った。ご相談させていただく事で心身ともに安心する事ができた。お困り事があれば何でも相談してほしいといった声掛けでより安心できる。
- 難病手当の減額問題について議会で取り上げてもらい、自分の話したことが政治に反映されたと感じた。
- 多岐にわたる部分で相談を持ち掛けていた。空き家問題や高齢者福祉、障がい者雇用、シングルマザー、相談してよいのか迷うほどの些細な事でも相談してきた。他の相談者からの案件も市議会議員としても相談を受けてくれる。
- 共通の知人の紹介を受け。評判が良い。支援者というより弟みたいな感覚がある。行動力もある。型にはまっていない自然体で聞く耳をもっている。医療や教育に関心があり、関心毎がリンクしている。住みやすい船橋を作ってほしい。
- 同級生のよしみで投票したが、あまり活動は知らない。都内で勤務していると市政の状況がわかりにくい。会に参加して津曲さんの市政活動が知れた。身近に感じにくい部分があるところをより知りたいと思うようになった。
- 飲み友達であり町会・商店会の活動で頑張ってもらっている
- 会の集まり等で問題ごとの解決を色んな人達の意見を徴収される機会を頻回に実施されているところがすごい。
- 地区社協の活動を一緒にしている。障害者と健常者が一緒にできるスポーツ(ボッチャ)スポーツに限らず共同できる事業をお願いしたい。
- ボランティア活動を一緒にしている。議員さんにここまで言って良いのか?と思い悩んでいたが今日の会に参加して今後は意見を伝えていきたい。
- 何度か相談事をさせていただき対応の早さが素晴らしい。
- 長く人付き合いをさせて頂きお人柄がとても良い。障がい者が住みやすい船橋になってほしいと思っている。また船橋は県内で視覚障害福祉の支援サービスが遅れている。
- ICT教育の面で船橋は遅れている。学校の先生がICTを活用しやすい環境づくり。授業に反映してほしい。ICT化の進んだ船橋市の学校教育の実現に期待している。
- サイバーセキュリティもしっかりして欲しい。
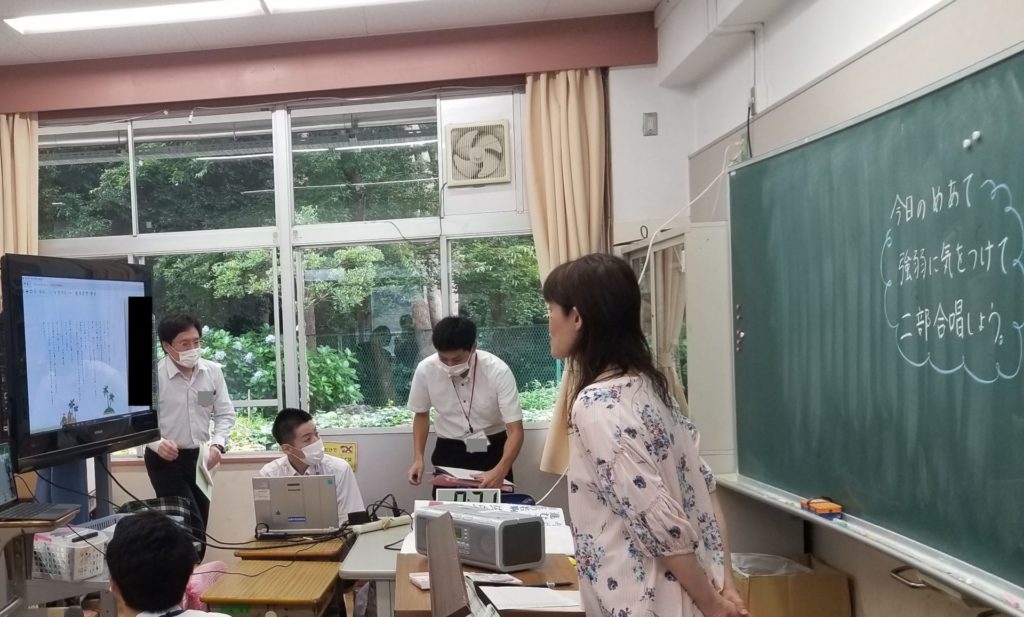
- 精神疾患の若年化を懸念している、未然に防止していく取り組みが大切。
- 子供子育て分野で頑張っているので応援している。SNSで必要な情報をリアルタイムで発信している。行政まで情報を取りにいかなくても良いので助かる。子供の教育や安全面でレスが早い。
- 市政や市の課題などはとっつきにくいと思っている。子供に障害があるが、通っている場所の居場所がないなどを感じる。
- 一緒に考え一緒に学びあえるインクルーシブな教育、社会が大切だと思っている。支援者の中には障害のある子育て世代が他にもいらっしゃる。会の参加が勉強の機会になっている。
- 市民一人一人の声が届く政治家があまりいないように感じている。政治についての自身の話を時間かけてゆっくり聞いてくれた。
- 医療センターの移転先が海老川付近で本当に大丈夫なのか心配。
- 行政に物申せるためには市民、現場の声の把握が一番大切。足と目と耳を使ってフットワークよく動き、市民のお困り事に積極的に対応する姿勢を10年間変わらず継続している。
- 船橋の一番の課題は道路問題であり、ここに取り組んで欲しい。

1時間半、様々なご意見やつまがりへの期待の背景などをじっくり聞かせていただきました。
フットワーク良く現場に足を運び、耳を傾けるという政治姿勢を変えず、これまで以上に障がい者施策・子ども達のことに力を入れて活動していきたいと思います。

